
3つのうま味成分の特徴をわかりやすく表にしてまとめます。
料理のおいしさを支えているのは、うま味という基本的な味の要素である。
普段料理をする方であれば感覚的にもご存じだと思うけれども、たとえばスープを作るときに砂糖や塩だけを使って頑張って味をととのえたところで、
「うーん、何か物足りないんだよなあ」
というような、なんだか表面的な味の完成物になってしまう。
そこにうま味が加わることで初めて、味わいに深みというものが出てくるわけだ。
今回は、代表的なうま味成分についてザッと学んでいこう。
主な3つのうま味成分をまとめる
うま味を感じさせるものとして代表的な成分は、次のとおりである。
- グルタミン酸(昆布のうま味)
- イノシン酸(かつおぶしのうま味)
- グアニル酸(干ししいたけのうま味)
「うま味」と一口に言っても実はその中にこうした種類があって、食材によってどのうま味成分を多く含むかも異なっている。
なお「うま味の相乗効果」と呼ばれる現象が知られていて、これらのうま味成分を単独で摂取するよりも、複数種類を組み合わせて摂取したほうが格段に強いうま味を感じられるという。
なるほど、たしかに和風だしをとるときって、昆布(グルタミン酸)とかつおぶし(イノシン酸)を両方使ってグツグツやったりしますね。
さて、それぞれの成分の特徴をまとめるとこんな感じ。
| 名 称 | グルタミン酸 | イノシン酸 | グアニル酸 |
| 発 見 者 | 池田 菊苗 (1864-1936) | 小玉 新太郎 (1885-1923) | 国中 明 (1928-2013) |
| 成分種別 | アミノ酸系物質 | 核酸系物質 | 核酸系物質 |
| メイン食材 | 昆布 | かつおぶし | 干ししいたけ |
| その他食材 | トマト、チーズ、 みそ、醤油など | 肉・魚全般など | キノコ全般、海苔など |
ここからは、各成分について個別に見ていこう。
グルタミン酸
グルタミン酸は、日本人研究者・池田菊苗(1864-1936)の功績によって世界で初めて「うま味成分」として認識されたことでも有名な、うま味界の代表格である。
これはタンパク質の構成要素であるアミノ酸の一種。
ほぼすべての動物や植物が体内で生成しているから、私たちが口にするほとんどの食材にはグルタミン酸が含まれているといってもいい。
ちなみに、人間の母乳の中にもグルタミン酸がたっぷり存在することが知られている。

そんなグルタミン酸を豊富に含む食材の代表は、昆布である。
60℃~70℃くらいのお湯でじっくり煮てやると、グルタミン酸がお湯の中にいい具合に溶け出していき、上品で優しい風味の昆布だしがとれる。
ほら、しゃぶしゃぶを食べるときなんかに、よく鍋の中に昆布の切れ端がペラっと沈んでるのを見ますよね。

イノシン酸
グルタミン酸がアミノ酸の一種だったのに対し、イノシン酸は核酸の一種である。
核酸というと遺伝子でおなじみのDNA(デオキシリボ核酸)が思い当たるが、イノシン酸も分子構造的にそれと親戚関係だということになる。
イノシン酸は特に動物性の食品に含まれることが多い。
なぜかというと、イノシン酸のおおもとは「生命エネルギーの通貨」ともいわれるATPにあるからだ。
生き物のエネルギーを媒介する物質。
私たち動物は、食事や呼吸によりATPを体内で生成し、貯まったATPをまた分解することで生命活動に必要なエネルギーを得ている。
動物が死ぬと、体内に貯まっていたATPが徐々に分解されていき、いくつかの過程を経たのちに、イノシン酸へと変化していく。
これがいわゆる熟成というやつで、食品を寝かせておくほどおいしさを増す仕組みである。
(ただし寝かせすぎるとイノシン酸がまた別の物質に変化し、今度は腐敗してしまう。)

イノシン酸を多く含むことで有名な食材として、かつおぶしがある。
薄ーく削ったかつおぶしを鍋にたっぷりいれて60℃~85℃のお湯で抽出するかつおだしは、香り華やかなうま味が特徴で、味噌汁やうどんのつゆなんかによく使われている。
また並んで和風だしの定番であるにぼしを煮出すとさらにパンチのある印象の風味となるが、これもかつおぶしと同じくイノシン酸によるうま味である。
グアニル酸
グアニル酸も、イノシン酸と同じく核酸系のうま味成分である。
こちらは一般的な動物・植物性の食材にはあまり含まれておらず、ほとんどしいたけやその他キノコ類の専売特許なのが特徴だ。

さらに厳しい条件として、グアニル酸を味わうためには生のしいたけではなく干ししいたけでなければならない。
なぜなら、生のしいたけにはグアニル酸のもととなる二つの素材である「RNA(リボ核酸)」とその「酵素」がバラバラに存在しているから。
しいたけを乾燥させて細胞を破壊することによってはじめてこの二者が出会い、めでたくグアニル酸を生成するわけだ。
また、だしをとる際の抽出方法にも注意が必要である。
昆布やかつおだしはお湯に浸して加熱することでうま味成分を抽出していたが、干ししいたけに関しては5℃程度の冷水を使ってじっくり抽出しなければならない。
これは、水が高温になるとグアニル酸を分解するような別の酵素が働いてしまうため。
食材の限定性といい抽出方法といい、グアニル酸はなにかと個性的なうま味成分といえるかもしれない。

この記事のおさらいクイズ
以上、代表的な3つのうま味成分のまとめでした。
ちなみに上記で挙げたものが全てではなく、それ以外にも様々なうま味成分の存在が知られている。
(コハク酸、アスパラギン酸、イボテン酸…など)
では最後に、この記事でみてきた知識をササっとおさらいしてみよう。
池田菊苗が「うまみ成分」の存在を発見するきっかけとなった食材は何でしょう?
正解:昆布(こんぶ)
1908年、池田菊苗はこんぶだしのうま味の正体がグルタミン酸であることを突き止め、ここから「うま味成分」の認識が世界に広がった。
干ししいたけなどに豊富に含まれている物質で、うま味成分として知られる核酸の一種は何でしょう?
正解:グアニル酸
グアニル酸は、しいたけなどのキノコ類を乾燥させることによって生成されるうまみ成分。
うま味成分の一つ「イノシン酸」のもととなる、生命活動においてエネルギーを媒介する役割をもつ物質は何でしょう?
正解:ATP(アデノシン三リン酸)
動物が体内に蓄えているATPが死後に分解されていく過程(熟成)によってイノシン酸が生成される。

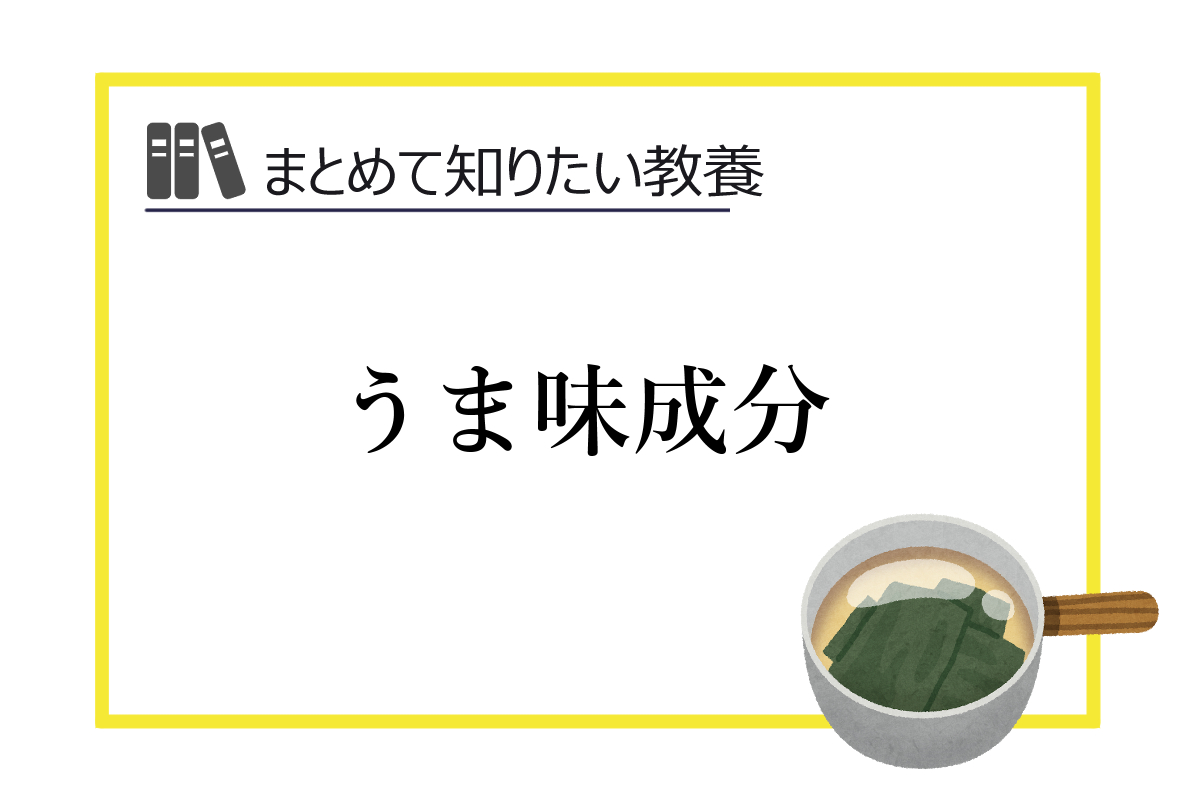


コメント