
物理学の論文によく出てくる温度の単位で「ケルビン」というものをご存じでしょうか。
絶対温度・ケルビンについて知ることで、「温度とは結局なんなのか」を理解することにつながります。
「ケルビン」という温度の単位がある。
私たちの普段の生活ではあまり耳にしないものの、物理学・化学の世界では広く用いられており、そうした分野の論文を読むとよく出てくる単位だ。
実はこのケルビン、去る2019年5月に、
「定義が改定されました!」
と話題になっている。
単位の定義が変わるというのはかなり歴史的なビッグイベントのように思えるけれど、いったいどうして今回わざわざ定義を変更する必要があったのか。
いや、その前にまずケルビンってそもそもなんなのか。
私たちがいつも使っている「摂氏」の温度とはどうちがうのか。
この記事ではザックリ誰でもわかりやすいアプローチで、そんな疑問を解消していきたい。
ケルビンってどんな単位?
尺度のポイントは「基準点」と「幅」
そもそもの話から考えてみよう。
温度とはいったいなにかというと、
「熱さや冷たさ、暑さや寒さに目盛をつけて、数字で表そう!」
という試みである。
これを実現するには、
- 「基準点」:どの熱さを何度と定めるか(=どこに基準を置くか)
- 「幅」:基準点からどのくらいの間隔で1度を刻んでいくか
を決めなければならない。
温度の単位の違いは、要するに「基準点」と「幅」の決め方の違いだということである。
摂氏(華氏)の場合
たとえば私たちになじみ深い「摂氏」は、
- 摂氏の「基準点」:①水が氷になる温度を「0℃」とする
②水が沸騰する温度を「100℃」とする - 摂氏の「幅」:① と ② の間を100等分した間隔 を「1度」とする
というルールによって成立した指標である。
また、アメリカでよく使われている「華氏」という温度の単位もこれと似ていて、
- 華氏の「基準点」:①水が氷になる温度を「32℉」とする
②水が沸騰する温度を「212℉」とする - 華氏の「幅」:① と ② の間を180等分した間隔を「1度」とする
というもの。
どちらも「水の状態変化」という共通の現象に着目して、基準に用いていることがわかる。
(摂氏と華氏についてはこちらの記事でより詳しく書いています)
ケルビンの場合
一方で、ケルビンのルールは摂氏や華氏とは一風変わっている。
- ケルビンの「基準点」:絶対零度を「0K(ケルビン)」とする
- ケルビンの「幅」:摂氏における「1度」を「1K(ケルビン)」とする
ケルビンが特徴的なのは、「水」のような特定の物質には関係なく、「絶対零度」という状態を基準点においていることである。
物質を構成する原子・分子の運動がほぼ完全に止まり、「これ以上の低温はない」状態となる温度のこと
絶対零度は摂氏でいうと「-273.15℃」にあたる。
そしてケルビンの幅は摂氏と同じ間隔をとるので、
【ケルビンでの温度(K)】 = 【摂氏での温度(℃)】 + 273.15
という非常にシンプルな関係が成り立つことになる。
このように原子・分子による熱力学法則に基づいて定義された温度を「絶対温度」という。
ケルビンは「絶対温度である」という点において、摂氏や華氏といった日常的な温度の単位とは一線を画す指標なのである。
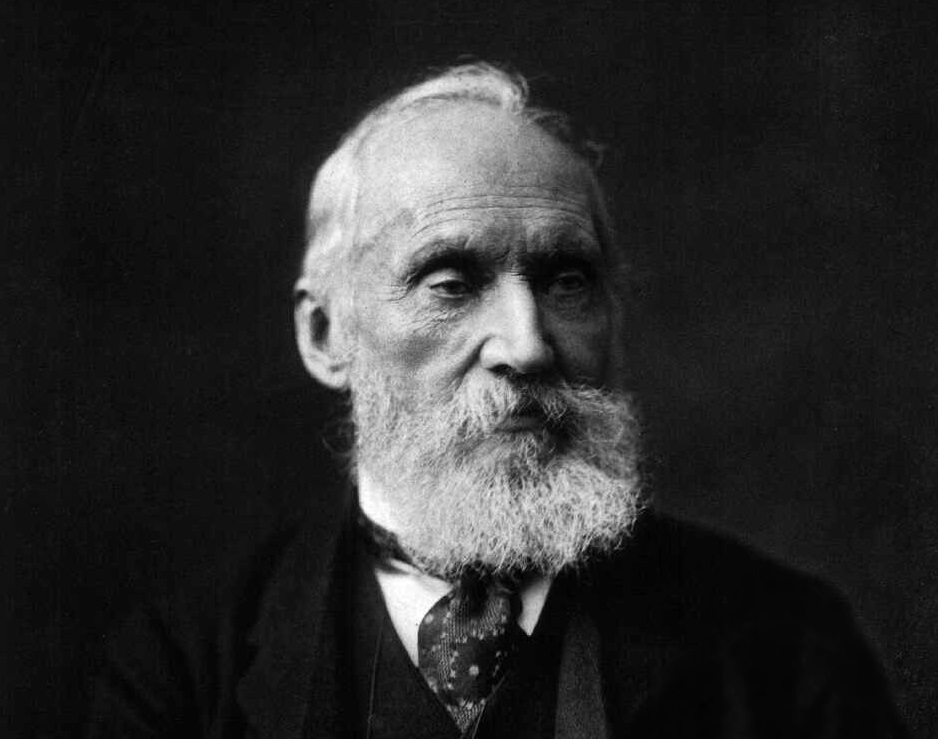
絶対温度ってどういうことだろう
私たちが普段使っている摂氏というのは、あくまで温度の世界を「水」というひとつの物質を通して見ているだけの、いわば主観的な指標である。
水が凍る温度を勝手に「0℃」と呼んでいるものの、別に「0℃」といっても決して「熱」が存在しないわけではない。
仮に冬の寒い日に「-20℃」を記録したとしても、「0℃」のときより熱の量が減っただけで、このときも「熱」そのものは確かに存在しているのである。
「じゃあ熱が “絶対的に” まったくゼロになることってあるの?」
と言われれば、それがまさしく「絶対零度(= -273.15℃ = 0K)」というわけだ。
摂氏はこのように主観的なモノサシに過ぎないので、
「お湯の温度が40℃から2倍に上昇して、80℃となりました!」
といった時の「2倍」は、熱力学的になんの意味もない数字である。
しかしケルビンのような絶対温度においてであれば、
「40ケルビンから2倍に上昇して、80ケルビンとなりました!」
という事実からは間違いなく「熱(エネルギー)の大きさが2倍に増加した」と説明することができるのだ。
改定されたケルビンの定義
ケルビンの新定義
上記のような「絶対温度」としての価値により、いまや物理学・化学の世界ですっかりスタンダードとなっているケルビンだが、2019年5月からはその定義が新しく定めなおされている。

まあ定義の変更といっても、
「今までの1ケルビンが新定義では1.5ケルビン相当になります!」
といった無茶な変更ではない。
「基本的には今までどおりだけど、『1ケルビンとは何か』の説明をちょっと違うアプローチで決めなおします!」
という感じだろうか。
その新定義が、コチラである。
ボルツマン定数を1.380649×10−23J/K とすることによって定まる温度
う、うーん?
いきなり何を言っているのでしょうか。
ここにきて急に突き放された感じがしてしまうが、慌てずザックリと噛み砕いていこう。
ボルツマン定数とは何か
ケルビンの新定義に突如姿を現した「ボルツマン定数」というのは、おおまかにいえば、
「温度」と「エネルギー」との関係をひもづけるような係数
と言い換えることができる。
具体的にはこれをつかって、
【エネルギー】 = 【温度(ケルビン)】 × 【ボルツマン係数】
という関係式を表せるのである。
すなわち、ボルツマン係数の値が定まっているとき、「その温度がどのくらいの熱の量(エネルギー)に相当するのか」をズバリ算出できる対応関係があるということになる。
そう考えると、ケルビンの新定義が主張しているのはつまり、
「エネルギーとの対応関係によって温度を定義しますよ」
ということなのだ。
ボルツマン定数を1.380649×10−23J/K とすることによって定まる温度
定義が変わったきっかけは
今回の定義変更のきっかけは、従来のケルビンの「幅」が水の状態変化に由来していることへの不満にあった。
< 科学者たちの意見>
- ケルビンの「基準点」:絶対零度を「0K(ケルビン)」とする
⇒ 妥当だね - ケルビンの「幅」:摂氏における「1度」を「1K(ケルビン)」とする
⇒ 何故いまだに主観的な摂氏に依存しているんだ!
ケルビンの「基準点」においては「絶対零度」という分子レベルの運動法則に注目しているわけだ。
しかしその「幅」に関しては、「水の融点と沸点の間を100等分」という、熱力学的にはナンセンスな目盛りを使い続けている。
科学が進歩し物質の運動がミクロレベルで研究できる今、
「ケルビンの幅についてももっと温度の本質をとらえた定義にすべきだ!」
という声があがっており、それが今回の新定義につながったわけである。
温度の本質はどこにある
温度とは分子の運動の度合い
では、科学者たちのいう「温度の本質」とはどういうことだろう。
「温度とは結局何か」ということだが、単刀直入に言えばそれは「物質を構成する分子たちがどのくらい運動しているかの度合い」である。
これはすなわち「エネルギー」と言い換えることもできる。
ご存じのとおりこの世のすべての物質はムチャクチャ小さい粒である「原子」でできており、それが集まって「分子」を構成しているわけだが、この分子は絶えずランダムに運動している。
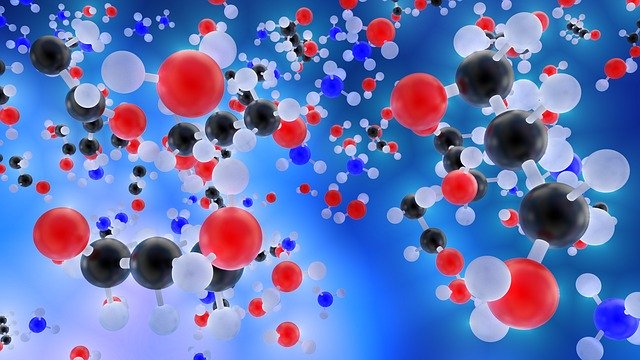
発射された大砲の球が破壊力をもつように、運動する分子もそれ相応のエネルギーをもつ。
分子の運動が激しくなればなるほど、それにしたがってエネルギーも大きくなっていく。
このエネルギーのことを私たちは「温度」と名前を付けて呼んでいるわけだ。
私たちは熱いものを触ると「やけど」をするけれど、あれは分子という小さな大砲の球のエネルギーを受けて、細胞が損傷しているということなんですね。
温度の正体は「熱さをつかさどる謎のパワー」ではなく、あくまで物理的な「分子の運動エネルギー」そのものだということだ。
エネルギーがようやく温度の定義へ
話を整理すると、つまりこういうこと。
分子は運動していて、「エネルギー」をもっている。
「エネルギーの大きさ」はすなわち「温度」と同義である。
(絶対零度においては分子の運動は止まり、エネルギーもゼロ)
しかしもはや慣習的には「温度」といえば「摂氏」であり、絶対温度ケルビンにおいても摂氏と同じく「水の融点と沸点との間を100等分したものが”1度”」というモノサシをすっかり使い慣れてしまっている。
そこで、「私たちがよく言う “1度” とはこのくらいのエネルギーのこと!」というのを示すボルツマン係数を登場させたのだった。
【エネルギー】 = 【温度(ケルビン)】 × 【ボルツマン係数】
【温度(ケルビン)】 = 【エネルギー】 / 【ボルツマン係数】
こうして「温度とはつまり分子の運動エネルギーである」という本質論を、みごと温度の定義に落とし込むことに成功したわけである。
考えてみれば、摂氏温度が提案された当時は、温度の正体が分子の運動だなんて誰にもわかっていなかったのだ。
(まだ分子の存在すら発見されていなかった。)
それが現代では、ミクロな物質の運動法則を語ることも可能になり、かつてボンヤリとしていた「温度」というものを明確に定義することができるようになった。
今回のケルビンの定義変更は、そんな科学の進歩の歴史をひしひしと感じられるトピックだったように思う。
□ケルビン(K)とは、絶対零度を基準点とした「絶対温度」の単位
・絶対零度(-273.15℃)= 0K
・1Kの幅は摂氏と同じ(水の融点と沸点の間を100等分したもの)
□近年ケルビンの定義が変更され、温度の本質(エネルギー)が反映される形となった
・ 新定義「ボルツマン定数を1.380649×10−23J/K とすることによって定まる温度」
⇒ 分子の運動エネルギーによって温度が定義されている




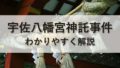
コメント